ブログ
Blog
Blog
お子さんが熱を出すと、
「熱を下げるために解熱剤を使った方がいいのかな?」
「どんな時に使えばいいんだろう?」
と、不安になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな疑問にお答えすべく、こどもの解熱剤について、パパママからよくいただく質問をQ&A形式でまとめてみました。エビデンスに基づきながらも、ご家庭で実践できる、分かりやすい情報をお届けします。
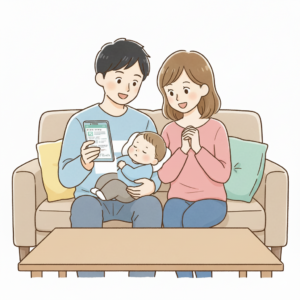
こどもの解熱剤として、小児科で一般的に処方されるのは主にアセトアミノフェンという成分です。 アセトアミノフェンは、熱を下げたり、痛みを和らげたりするお薬です。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症の時にも安全に使用できることから、世界的に広く使われています。
大人では、ロキソプロフェンやジクロフェナクナトリウムという成分が使用されますが、これらは重篤な副作用を引き起こす可能性があるため、基本的には15歳未満の小児には使用しません。
はい、アセトアミノフェンは、乳児にも安全に使用できるお薬です。
当クリニックでは、生後6ヶ月以降のお子さんから処方することが多いです。特に小さいお子さんでは、体重に合わせて厳密に量を計算する必要がありますので、自己判断で使用せず、必ず医師の指示に従ってください。
主に次の3つの剤形があります。
基本的には、どの剤形でも効果に大きな違いはありません。
ただし、効果の現れ方には少し差があります。一般的に、シロップや粉薬などの内服薬は、坐薬に比べて効果が出るまでに少し時間がかかります。坐薬は直腸から直接吸収されるため、比較的早く効果が現れやすいと言われています。
お子さんの状態に合わせて使い分けます。
いいえ、必ず使う必要はありません。
解熱剤は、「熱を下げる」ことが目的ではなく、「熱によるつらさを和らげる」ことが目的です。 体温が38.5度以上で、つらそう、眠れない、水分がとれない、などの場合に、一時的に楽にしてあげるために使用します。
解熱剤の使用が病気の治癒を遅らせるという明確なエビデンスはありません。
何度以上という明確な基準はありません。
これは、お子さんの状態が最も重要な判断基準だからです。例えば、40℃の熱があっても、元気で機嫌が良ければ、解熱剤を使う必要はありません。逆に、38℃台でも、ぐったりして水分がとれない、眠れない、つらそうにしている、といった場合には使用を検討します。
当クリニックでは、体温が38.5度以上で、つらそう、眠れない、水分がとれない、などの場合に、一時的に楽にしてあげるために使用しましょうと指導しています。
一般的には、6時間以上の間隔をあけて使用します。
使用間隔が短すぎると、薬の成分が体の中に過剰に蓄積し、肝臓に負担をかけてしまう可能性があります。 必ず、お薬の袋に記載されている用法・用量を守りましょう。
薬を飲んですぐ(だいたい30分以内)に吐いてしまった場合
→再度同じ量を飲ませるのが一般的です。
薬を飲んで30分以上が経過してから吐いた場合
→どれだけの量が体内に吸収されたか分からず、もしすぐに飲み直してしまうと、過剰摂取になる恐れがあるため、追加の内服はやめ、次の服薬タイミングに使用するか検討しましょう。
使用後、30分以内に坐薬がそのままの形で出てきてしまった場合は、もう1個入れ直しても大丈夫です。
座薬を入れてから30分以上経過した場合は、追加の使用はやめて、次の服薬タイミングに使用するか検討しましょう。
必ずしも重症というわけではありません。
解熱剤を使用しても熱が下がらないことは、しばしばあります。特に、ウイルスや細菌の勢いが強い時は、解熱剤の効果が一時的だったり、十分に熱が下がらないこともあります。
熱が下がらないこと自体よりも、「お子さんの様子」をよく観察することが重要です。
このような様子が見られる場合は、すぐに医療機関を受診してください。
残念ながら、解熱剤で熱性けいれんを予防することはできません。
熱性けいれんは、体温が急激に上昇する時に起こりやすいと言われています。解熱剤は、熱の上昇を緩やかにする効果はありますが、完全に防ぐことはできません。 熱性けいれんの既往があるお子さんは、かかりつけの先生と相談し、必要がある場合はけいれんを予防するお薬(ダイアップ坐剤など)を処方してもらい、正しく使用することが大切です。
アセトアミノフェンはほとんど副作用がなく比較的安全なお薬です。ごくまれに次のような副作用が起こることがあります。
適切な用量を守って使用すれば、副作用のリスクはほとんどありません。
そのようなエビデンスはありません。
日本小児科学会JPSや米国小児科学会AAP、米国産科婦人科学会ACOG、イギリス医薬品・医療製品規制庁MHRA、欧州医薬品庁EMAなど、公的な機関は、妊婦のアセトアミノフェン使用を制限する勧告は出していません。 妊娠中の発熱や痛みには、まずアセトアミノフェンを使用することが推奨されています。
情報の真偽を確かめる際は、公的機関や信頼できる医療機関の情報源を確認することが重要です。
今回のQ&Aが、パパママの皆さんの不安を少しでも和らげ、お子さんの看病に役立つことを願っています。ご不明な点があれば、いつでも当クリニックにご相談ください。
【SNSでも情報発信中!】
当院のSNSでは、小児科・皮膚科に関する役立つ情報や、季節ごとの病気の注意点などを発信しています。ぜひフォローしてください!
Instagram: 武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科
当院の外観写真
日本医科大学医学部 卒業、順天堂大学大学院・医学研究科博士課程修了、国立国際医療研究センター小児科勤務、東京女子医科大学循環器小児科勤務
医学博士、日本小児科学会小児科専門医、日本小児科学会指導医、日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医、そらいろ武蔵小杉保育園(嘱託医)、にじいろ保育園新丸子(嘱託医)
© Morino Kodomo Clinic

