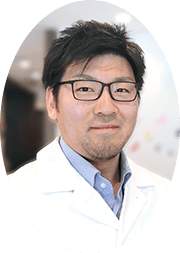当院は日本小児科学会認定小児科専門医、そして日本皮膚科学会認定皮膚科専門医が、お子さんの様々な症状に対応しています。今回は夏に流行する代表的な皮膚の感染症「とびひ(伝染性膿痂疹)」について、おうちでできるケアも含めてお話ししていきたいと思います。
夏になると、お子さんの皮膚トラブルが増えますね。虫刺されをかきむしったり、小さなキズから細菌が入り込んでしまったり。
「うちの子、なんだか体に水ぶくれができてるみたいで…」
「かゆがって、かきむしっちゃって…」
そういったお悩みで受診される方も多いのが、この「とびひ」です。
正式名称は「伝染性膿痂疹(でんせんせいのうかしん)」といいます。なんだか難しそうな名前ですが、その名の通り、人から人へ、そして体のあちこちに「伝染」していく、感染力の強い皮膚の病気です。

とびひって、どんな病気?
とびひは、おもに「黄色ブドウ球菌」や「溶血性レンサ球菌」といった細菌が皮膚に感染して起こる病気です。これらの細菌は、健康な人の鼻や皮膚にも普段から存在していますが、皮膚にキズがあったり、汗でふやけていたりすると、そこから入り込んで炎症を起こしてしまうんです。
とびひには大きく分けて2つのタイプがあります。
1. 水ぶくれができる「水疱性膿痂疹(すいほうせいのうかしん)」
夏場に多く見られる、子どもに多いタイプです。
最初は赤みのある小さなプツプツや水ぶくれができます。かゆみが強いため、お子さんはここをかきむしってしまいます。すると、水ぶくれが破れてジュクジュクした液(滲出液)が出てきます。この滲出液の中には細菌がたくさん含まれていて、触った手で体の別の場所を触ると、そこにもうつってしまい、まるで火事が飛び火するように症状が広がっていくことから「とびひ」と呼ばれるようになりました。
顔や頭、手足などによくできます。とくに乳幼児に多く、夏場に汗をかきやすいお子さんは注意が必要です。
2. カサブタができる「痂皮性膿痂疹(かひせいのうかしん)」
こちらは、一年を通して見られるタイプです。水ぶくれはできずに、最初から皮膚が赤くなり、膿(うみ)をもったカサブタ(厚い黄色や茶色のカサブタ)ができます。
とびひ全体から見ると数は少ないですが、アトピー性皮膚炎やアレルギー疾患をもっているお子さんに起こりやすいと言われています。また、溶血性レンサ球菌という細菌が原因の場合、ごくまれに腎臓に影響を及ぼす合併症を起こすこともあるため、注意が必要です。
どちらのタイプも、早期に適切な治療を開始することが大切です。
とびひかな?と思ったら、どうすればいいの?
もしお子さんの体に水ぶくれやカサブタ、ジュクジュクした部分を見つけたら、早めに小児科や皮膚科を受診しましょう。
「たかが水ぶくれ」と軽く考えず、他の場所に広がってしまう前に相談してください。
とびひの治療法は?
とびひの治療の基本は、飲み薬と塗り薬です。
- 抗菌薬の飲み薬:とびひの原因となっている細菌を体の中からやっつけます。
- 抗菌薬の塗り薬:皮膚の患部に直接塗って、細菌の繁殖を抑えます。
症状が軽い場合は塗り薬だけでも治ることがありますが、広範囲に広がっている場合や、水疱性ではないタイプの場合は、飲み薬も併用することが一般的です。
おうちでできる「とびひ」のホームケア
病院で診てもらい、お薬をもらったからといって安心はできません。とびひの治療には、ご家庭でのケアがとても重要です。
1. 患部は清潔に保つ
とびひを治すためには、何より患部を清潔に保つことが大切です。
「お風呂に入ると、他の場所にうつっちゃうんじゃないか…」と心配される親御さんもいますが、それは間違いです。シャワーや石鹸で患部をきれいに洗い流しましょう。
ただし、ゴシゴシこするのは厳禁です。泡立てた石鹸で優しく洗い、シャワーで洗い流すようにしてください。洗った後は、清潔なタオルで患部をそっと押さえるように拭き取ります。
2. 患部を保護する
かきむしってしまうと、とびひはどんどん広がってしまいます。
- 患部をガーゼや包帯で覆って、直接触らないようにしましょう。
- お子さんの爪はこまめに短く切って、清潔に保ちましょう。
- 赤ちゃんや小さなお子さんの場合は、ミトンなどをつけるのも有効です。
3. タオルや衣類は共有しない
とびひは感染力が強い病気です。家族への感染を防ぐためにも、以下のことを徹底しましょう。
- お風呂のタオルやバスタオルは、患部を拭いたものと分けて使用する。
- 衣類はこまめに着替えさせ、他の家族のものとは分けて洗濯する。
- お子さんが触ったおもちゃも、こまめに拭いて清潔を保つ。
とびひにかかったら、保育園や学校は休むべき?
これは親御さんが一番悩まれるところかもしれません。
とびひは、原則として完治するまでは登園・登校を控える必要があります。
しかし、「どうなったら完治なの?」という疑問も湧いてきますよね。
当院では、以下の状態になったら登園・登校の許可を出しています。
- 患部をきちんとガーゼなどで覆うことができる。
- 患部からジュクジュクした液(滲出液)が出ていない。
- 医師から許可が出ている。
まずは医療機関を受診して、医師の指示に従ってください。無理に登園・登校させてしまうと、他のお子さんにとびひがうつってしまい、迷惑をかけてしまうことになります。
とびひを予防するには?
とびひは、日々の生活の中で予防することができます。
1. 毎日しっかり手洗い・うがいをする
とびひの原因となる細菌は、普段から手のひらに付着していることが多いです。帰宅後や食事の前には、しっかりと手洗いを習慣づけましょう。
2. 皮膚のキズを放置しない
虫刺されや小さなキズからとびひは始まります。キズができたら、まずは石鹸で優しく洗い、清潔な状態を保ちましょう。
3. 汗をかいたらシャワーを浴びる、着替える
夏場は汗をかきやすく、皮膚がふやけて細菌が入り込みやすい状態になります。汗をかいたらこまめにシャワーを浴びたり、着替えをしたりして、皮膚を清潔に保ちましょう。
まとめ
とびひは、夏の皮膚トラブルの代表格ですが、正しい知識と適切なケアで、広がっていくのを防ぐことができます。「もしかして、とびひかも…?」と思ったら、ためらわずに、まずはかかりつけ医にご相談ください。
「武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科」では、お子さんの皮膚のトラブルに専門的に対応しています。
「これって、とびひ?それとも違う病気?」
迷ったときには、ぜひ一度当院皮膚科までご相談ください。
当院皮膚科・小児皮膚科は日時指定の予約制です。発熱患者さんとは別のクリーンな待合室と診察室で対応しています。Web予約サイトの「皮膚科」タグからご予約を取得していただくとともにWeb問診の入力をおねがいいたします。
【SNSでも情報発信中!】
当院のSNSでは、小児科・皮膚科に関する役立つ情報や、季節ごとの病気の注意点などを発信しています。ぜひフォローしてください!
Instagram: 武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科

当院の外観写真
川崎市中原区
アクセス:武蔵小杉、新丸子、元住吉、武蔵中原、日吉
武蔵小杉 森のこどもクリニック小児科・皮膚科
日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
診療チーム